MT-07は酷評されているのか気になっているあなたは、MT-07の購入や乗り換えを検討する中で、不安や疑問を感じているのではないでしょうか。
ヤマハのMT-07は、軽快な走行性能とコストパフォーマンスの高さで人気を集める一方で、さまざまな意見が寄せられているモデルでもあります。
特に、フル加速時の挙動や段差で「跳ねる」と感じるサスペンション特性に不満を持つ声、レギュレーターなどの持病とされる不具合に関する情報、購入後に後悔したというリアルな体験談などは事前に把握しておきたいポイントです。
さらに、MT-07の海外評価と国内の反応には違いもあり、そのギャップに驚く方もいるかもしれません。
中古市場での選び方や、2025年の新型モデルで何が改善されたのかも注目されています。
また、カスタムでツアラー化を考えている方にとっても、メリット・デメリットを知ることは重要です。
この記事では、MT-07に対する酷評やその理由を冷静に分析しつつ、どんなライダーに合うバイクなのか、後悔しないための判断材料をわかりやすく解説していきます。
ポイント
-
MT-07のフル加速時や段差での跳ねる挙動について
-
持病とされる故障例や購入後の後悔ポイント
-
海外評価と日本での評価の違い
-
ツアラー化などのカスタムや新型2025モデルの注目点
【PR】いまいくら?バイク王で30秒査定してみませんか?
- いま、いくら?カンタン30秒で無料査定|出張0円・査定0円
- たった5問で完了|プロが最新相場をご案内(24時間365日受付)
- 相談実績300,000件※|まずは無料で相場チェック
スポンサーリンク
MT-07 酷評の理由を初心者向けに解説

出典:YAMAHA公式サイト
フル加速時のフィーリングに賛否
MT-07の加速性能については、多くのライダーから高評価を得ている一方で、一部ではネガティブな意見も見られます。
つまり「フル加速時のフィーリング」には明確な賛否があるということです。
そもそもMT-07は、並列2気筒の688ccエンジンを搭載しており、車体の軽さと相まって非常に鋭い加速を実現しています。
アクセルを大きく開けたときの瞬発力は、大型バイクとしては扱いやすい部類に入りつつも、スロットルに対して敏感に反応するため、初めての大型バイクとしてはややピーキーに感じられることもあります。
この加速の特徴を「楽しい」と受け取るか、「怖い」と感じるかは、ライダーの経験や好みによって大きく分かれます。
例えば、街中から高速道路への合流、あるいは山道でのスポーツライディングでは、MT-07のキビキビとした加速がとても頼もしく感じられるでしょう。
一方で、まったり走りたい人や、直線安定性を重視する人にとっては「落ち着きがない」と捉えられてしまう場合もあります。
また、加速時に前輪が浮きやすいという声もあります。
これは車体が非常に軽量で、前後重量配分がフロント寄りではないことに起因しています。
ある程度のテクニックがないと、意図しないウイリーに繋がる可能性もあるため、ビギナーには注意が必要です。
このように、MT-07のフル加速時のフィーリングは、パワフルさと軽快さを求めるライダーにとっては大きな魅力ですが、穏やかな乗り味を好む方には合わない場合があります。
試乗やレンタルなどで実際に体感してから判断することをおすすめします。
「跳ねる」挙動とは何か
MT-07に関する酷評の中でも、比較的多くの声が寄せられているのが「跳ねる」挙動に関するものです。
これは特にフロントサスペンションに起因するフィーリングの違和感を指す言葉として使われています。
まず、MT-07はコストパフォーマンスに優れたモデルとして設計されており、サスペンションもそれに応じた仕様となっています。
具体的には、フロントフォークは非調整式の正立フォークであり、ダンパー性能がややマイルドです。
このため、荒れた路面や段差を越えた際に、衝撃が収まりにくく「跳ねる」ような挙動を見せることがあります。
特にワインディングロードやサーキットのようなスピードレンジの高い場面では、そのサスペンションの特性が如実に現れやすくなります。
しっかりと減速してコーナーに進入したつもりでも、バイクが路面の凹凸を拾って前後にバウンスするような動きを感じる人もいるでしょう。
こうした挙動は、ライディング時の安心感に直結する要素であり、スポーツ志向のライダーには不満につながるポイントです。
一方で、街乗りレベルの速度域であれば、サスペンションの柔らかさはむしろ快適さに寄与することもあります。
乗り心地がソフトなため、段差やマンホールの上を通過する際にもガツンとした衝撃は少なく、初心者でも扱いやすいフィーリングを得られます。
このように、MT-07の「跳ねる」挙動はその構造的な特徴に由来するものであり、ライダーの用途や求める性能によって感じ方が大きく異なります。
もしスポーツ走行を主目的とするなら、サスペンションのカスタムを前提に考えるのが現実的でしょう。
購入後に後悔する人の主な理由

MT-07は多くのファンを持つバイクでありながら、購入後に「後悔した」と語る人も少なからず存在します。
ここでは、そうした声の中でも特に多い理由を3つに分けて紹介します。
第一に挙げられるのが「足回りの物足りなさ」です。
前述のように、MT-07のサスペンションは価格を抑えた仕様となっており、本格的なスポーツライディングには不向きと感じる人がいます。
購入当初は街乗り中心でも、後々ツーリングや峠道を積極的に楽しみたくなったとき、足回りの不安定さが気になり始め、結果として買い替えやカスタムを検討するケースも多いようです。
次に「ライディングポジションの合わなさ」も後悔の原因となります。
MT-07はアップライトなポジションを基本としていますが、長距離のツーリングでは疲れやすいと感じる人もいます。
また、身長や体格によってはハンドルやシートの位置がしっくりこず、快適な姿勢を維持できないことがあります。
そしてもう一つは「見た目や所有感への不満」です。これはMT-07がシンプルなデザインを採用していることに関係しています。
実用性重視で設計されているため、豪華な装備や目立つ装飾が少なく、他の大型バイクと比べると「物足りない」と感じる場合があります。
特に、見た目にもこだわりたいライダーにとっては、購入後に思っていた印象と違っていたと後悔する原因になりかねません。
このように、MT-07を購入後に後悔する理由は、性能・快適性・デザインといった複数の要素に起因しています。
事前に自分の用途や好みを明確にし、試乗やカスタムの可能性を含めて慎重に検討することが、後悔を避けるための鍵となるでしょう。
MT-07に見られる持病の実態
MT-07は、コストパフォーマンスに優れたミドルクラスバイクとして多くの支持を集めていますが、一部のユーザーからは「持病」と呼ばれるような共通トラブルについての報告も見受けられます。
これは設計上の特徴や、部品の品質、整備の頻度などが関係しているケースが多く、購入を検討している方はあらかじめ把握しておくことが重要です。
特に多く挙げられるのが「レギュレーターの不調」です。
これは発電系統に関する部品で、電圧の安定を担っています。
不具合が生じると、バッテリーへの充電がうまく行われず、走行中にエンジンが止まってしまうリスクもあります。
こうした症状は、長距離ツーリングや夜間走行中に発生すると非常に危険です。
定期的な電圧チェックや、予防的な交換を視野に入れるライダーも少なくありません。
次に、スロットルのレスポンスに関する問題も「持病」として語られることがあります。
アクセル操作に対してラグを感じる、あるいは微妙なコントロールがしにくいという声です。
これはECU(エンジン制御ユニット)のセッティングによる影響が大きく、街乗りでは気にならないことが多いものの、ワインディングやサーキットのように繊細な操作が求められる場面では、不満を感じる可能性があります。
他にも、タンクカバー周辺のビビリ音や、リアショックからの異音といった細かなトラブルも報告されています。
いずれも致命的な問題ではないものの、バイクとの長期的な付き合いを考えるなら、気になる要素です。
このように、MT-07に見られる持病にはいくつかの傾向がありますが、事前に情報を得ておくことで対策や予防が可能になります。
購入後に不安を抱えないためにも、納車前の点検内容を販売店にしっかり確認したり、整備の記録がある車両を選ぶことが望ましいでしょう。
中古は本当にお得なのか

MT-07は新車価格が比較的手頃なこともあり、中古市場でも人気の高いモデルです。
しかし「中古車はお得なのか?」という点については、一概にイエスとは言えません。
価格だけでなく、走行距離や整備履歴、カスタム内容などを総合的に判断する必要があります。
まず価格面で見ると、MT-07の中古相場は年式や走行距離によって大きく異なります。
初期型であれば30万円台から見つかることもありますが、走行距離が多い車両や、外装に傷みがあるものも含まれるため、安い=お得と判断するのは危険です。
また、2020年以降のモデルになると装備のアップデートも進んでおり、中古でも50万円〜70万円ほどの価格帯になるケースが多いです。
さらに注意したいのが、メンテナンス状態です。
MT-07は比較的シンプルな構造を持つバイクではあるものの、消耗品の交換や定期的な整備を怠るとトラブルの原因になります。
例えば、ブレーキパッドやチェーン、タイヤなどの消耗が進んでいる中古車を選んでしまうと、購入後すぐに数万円単位の追加費用が発生することもあります。
一方で、中古車ならではのメリットもあります。
すでにETCやUSBポート、社外マフラーといったカスタムが施されている車両も多く、それらが好みに合えば初期費用を抑えつつ、自分好みの仕様を手に入れられる可能性もあります。
とはいえ、カスタム内容によっては整備が難しくなったり、逆にパーツの劣化が早まる場合もあるため、事前の確認が不可欠です。
最終的に、中古のMT-07が「本当にお得」かどうかは、その車両の状態と、購入後の使用目的・予算にどれだけマッチするかにかかっています。
価格だけで判断せず、バイクショップの保証制度や整備内容の説明をしっかり受けることが、後悔しない中古購入への第一歩になるでしょう。
最新モデルでもMT-07に酷評の声はある?

出典:YAMAHA公式サイト
新型2025年モデルの変化点とは
2025年モデルのMT-07は、デザインや装備面において複数の改良が施され、従来モデルとの差別化が進んでいます。
これまでのMT-07が持つ特徴を残しつつも、より現代的な仕様へとアップデートされているのが注目ポイントです。
まず外観デザインについては、フロントフェイスの変更が大きな特徴となっています。
新たに採用されたLEDヘッドライトユニットは、より鋭角で攻撃的な印象を与えるデザインになっており、従来型よりも近未来感を強く打ち出しています。
この変更によって、MTシリーズらしい「ストリートファイター」的な雰囲気が一層強調されています。
また、メーター周りも刷新され、TFT液晶ディスプレイが採用されています。
視認性が向上しただけでなく、スマートフォン連携による通知表示やナビゲーション対応など、電子制御面での利便性が格段に向上しました。
これはツーリング志向のユーザーや、デジタル機能を重視する若年層にとっては大きな魅力となるでしょう。
さらに、ブレーキ性能の向上や、サスペンションのセッティング見直しといった走行性能のブラッシュアップも行われています。
これにより、従来モデルで指摘されていた「跳ねる」「フワつく」といった乗り味がやや改善されていると報告されています。
とくに高速道路やワインディングでの安定感が向上しており、より幅広いライダー層にフィットする仕様へと変化している印象です。
このように、2025年モデルのMT-07は、見た目の刷新だけでなく、装備や走行性能においても確実な進化を遂げています。
従来型を検討していた人にとっても、少し待って新型を選ぶ価値は十分にあると言えるでしょう。
もちろん、予算やカスタムの自由度を考えると旧モデルにもメリットはありますが、新型が持つ最新装備の数々は、今後のスタンダードになる可能性を秘めています。
ヤマハ MT-07(2025年)スペック表
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 車名 | MT-07 |
| 型式/原動機打刻型式 | 8BL-RM48J/M427E |
| メーカー希望小売価格 | 968,000円(税込)/本体価格 880,000円(税抜) |
| 全長×全幅×全高 | 2,065mm × 780mm × 1,110mm |
| シート高 | 805mm |
| 軸間距離 | 1,395mm |
| 最低地上高 | 150mm |
| 車両重量 | 183kg |
| 定地燃費値(60km/h・2名) | 39.8km/L |
| WMTCモード値(1名) | 25.4km/L(クラス3 サブクラス3-2) |
| エンジン種類 | 水冷・4ストローク・DOHC・4バルブ |
| 気筒数配列 | 直列2気筒 |
| 総排気量 | 688cc |
| 内径×行程 | 80.0mm × 68.5mm |
| 圧縮比 | 11.5:1 |
| 最高出力 | 54kW(73PS)/8,750rpm |
| 最大トルク | 68N・m(6.9kgf・m)/6,500rpm |
| 始動方式 | セルフ式 |
| 潤滑方式 | ウェットサンプ |
| エンジンオイル容量 | 3.00L |
| 燃料タンク容量 | 13L(無鉛レギュラーガソリン) |
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション |
| 点火方式 | TCI(トランジスタ式) |
| バッテリー | 12V/6.0Ah(YTZ7S) |
| 一次減速比/二次減速比 | 1.925 / 2.687(77/40 × 43/16) |
| クラッチ形式 | 湿式・多板 |
| 変速方式 | 常時噛合式6速/リターン式 |
| 変速比(1〜6速) | 2.846/2.125/1.631/1.300/1.090/0.964 |
| フレーム形式 | ダイヤモンド |
| キャスター/トレール | 24°20′ / 93mm |
| タイヤサイズ(前/後) | 120/70ZR17M/C(58W)/180/55ZR17M/C(73W)※チューブレス |
| ブレーキ形式(前/後) | 油圧式ダブルディスク/油圧式シングルディスク |
| サスペンション(前/後) | テレスコピック/スイングアーム(リンク式) |
| ヘッドランプ | LED |
| 乗車定員 | 2名 |
| 製造国 | 日本 |
海外評価は日本と違う?

MT-07は世界中で販売されているヤマハのグローバルモデルであり、各国で異なる評価を受けていることが興味深い点です。
特に欧米市場では、MT-07は「ミドルクラス最強コスパのネイキッドバイク」として高く評価されており、日本国内で見られる一部の酷評とは少し印象が異なります。
アメリカやヨーロッパのライダーからは、その軽量さと扱いやすさが特に好評です。
街乗りはもちろん、ワインディングロードでの走行性能も高く評価されており、「フレンドリーでパワフルなバイク」として紹介されることが多くあります。
実際、アメリカでは大型免許の取得ハードルが日本より低いため、初めての大型バイクとしてMT-07を選ぶ人が非常に多い傾向にあります。
一方で、海外でも批判がまったくないわけではありません。
特にサスペンション性能については、ややソフトすぎるとする声が少なくありません。
これは高速域での安定感や、峠道での限界走行時に「足りなさ」を感じるという意見につながっています。
また、ブレーキのタッチに対しても「もう少しダイレクト感が欲しい」とするライダーも一定数います。
こうした評価の違いの背景には、道路環境やライディングスタイルの違いが影響していると考えられます。
例えば、欧州では高速道路や郊外の快走路を長距離走る機会が多く、快適性と安定性がより重視される傾向があります。
そのため、MT-07の軽快なハンドリングが「楽しい」と感じられる一方で、「荒さ」を感じるケースもあるのです。
このように、MT-07は海外でも高い人気を誇る一方で、使用環境やライダーの期待値によっては賛否が分かれる面もあります。
日本国内での評価との違いを理解することで、より多角的にこのバイクを捉えることができるようになるでしょう。
ツアラー化カスタムの課題と利点
MT-07を「ツアラー仕様」にカスタムする人が増えています。
これは、もともと軽量で機動性に優れたMT-07の特性を活かしつつ、長距離走行にも対応できる快適なバイクへと仕立てる目的があります。
実際、パニアケースの装着、スクリーンの追加、シートの交換といったカスタムは比較的容易に行えるため、ユーザーの手で旅仕様に進化させる例も珍しくありません。
ツアラー化の利点は明確です。
まず、長距離ツーリングでの疲労軽減に直結する装備を加えられること。
例えば、風の巻き込みを抑える大型スクリーンや、座り心地を改善するゲルシートへの変更などは、長時間のライディングにおける快適性を大きく向上させます。
また、パニアケースやリアボックスを装備すれば積載性もアップし、キャンプツーリングや一泊旅にも対応できるバイクになります。
しかしながら、こうしたカスタムには課題もあります。
最大の懸念は、MT-07本来の「軽快さ」が損なわれる可能性があるという点です。
装備を追加することで車重が増加し、ハンドリングが鈍くなるケースがあります。
特にフロント周りに重量物を加えると、旋回性や操作感が変化し、元々の軽快なキャラクターが薄れることがあります。
また、コスト面でも注意が必要です。
純正品にこだわらずとも、信頼できる社外品を揃えるとなれば、トータルで10万円以上の出費になることも珍しくありません。
そのため、ツアラー化を検討する際には、自分が本当に長距離用途を重視しているのか、あるいは普段の街乗り中心なのかをよく見極めることが大切です。
このように、MT-07のツアラー化は確かに魅力的な選択肢ではありますが、その反面、装備追加による重量増やコスト増というデメリットも存在します。
バイク本来のキャラクターとのバランスを取りながら、自分に合ったカスタムを行うことが、満足度の高いツーリングライフにつながると言えるでしょう。
初心者に本当に向いている?

MT-07は「初心者におすすめ」とされることが多いバイクですが、その評価がすべての人に当てはまるとは限りません。
確かに、取り回しやすい軽さ、扱いやすいパワー特性は、ビギナーにとって安心できる要素ですが、注意すべき点もいくつか存在します。
まずポジティブな面としては、重量が約180kg台と比較的軽く、足つきも良好な点が挙げられます。
これは、街乗りやUターン時の負担を大きく軽減してくれるため、バイクに不慣れな人でも安心して取り回すことができます。
さらに、トルクの出方も低回転から滑らかに立ち上がる特性があり、「回さなくても走れる」エンジンとして初心者に好評です。
一方で、MT-07には扱いやすさの中に潜む“クセ”もあります。
特にクラッチ操作がややダイレクトなため、発進時にギクシャクしてしまうという声も聞かれます。
また、アクセル開閉に対する反応が敏感で、低速域でのラフな操作がギクシャクした動きにつながることもあります。
これは、まだバイクの挙動に慣れていない初心者にとってはややハードルが高いと感じるポイントです。
さらに、MT-07は排気量が689ccの大型バイクである以上、公道では十分すぎるほどのパワーを持っています。
そのため、慣れるまではアクセルの開け方に注意が必要で、気を抜くと一気に加速してしまうことがあります。
このような特性を理解しないまま乗り始めてしまうと、操作ミスや恐怖感につながることも考えられます。
このように考えると、MT-07は初心者にも適したバイクであることは間違いありませんが、「どの程度の経験があるか」によって向き・不向きが分かれます。
教習所での練習しか経験がない完全なビギナーよりも、小排気量バイクである程度走行経験を積んだ人の“次の一台”として選ぶ方が、より満足度の高い結果につながるでしょう。
購入前に知るべき短所
MT-07は多くのライダーから高評価を得ている一方で、購入後に気づく短所もいくつか存在します。
事前にこうしたデメリットを理解しておくことで、「想像と違った」と感じるリスクを減らすことができます。
まず第一に挙げられるのが、足回りの柔らかさです。
特にサスペンションは、街乗りやゆったりしたツーリングには向いていますが、スポーツ走行やワインディングでのアグレッシブな走りを求める場合、物足りなさを感じやすい部分です。
コーナーでの安定感やフロントの接地感が弱く、サスペンションの底付きも起こりやすいため、「もっとしっかりした足回りが欲しい」と感じる人も少なくありません。
次に、ブレーキ性能についても意見が分かれます。
制動力自体は必要十分といえるものの、タッチがやや曖昧で、特に前輪ブレーキの感触に「もう少しカッチリしてほしい」といった声が上がります。
これは繊細な操作を好むライダーにとっては気になるポイントとなるでしょう。
また、タンデムや積載性を重視する人にとっては、シートの硬さやリア周りの設計がネックになる場合もあります。
純正状態では長時間の2人乗りや荷物の搭載に向かない構造であるため、ツアラー志向のライダーはカスタムを視野に入れる必要があります。
さらには、振動の問題も見逃せません。
並列2気筒のクロスプレーンエンジンは低中速で力強く鼓動感もあるものの、特定の回転域で細かい振動が発生し、長距離走行では手やお尻に疲れを感じやすいといった意見があります。
これらの短所は、使用目的や乗り手の期待値によっては気にならない場合もあります。
ただし、MT-07を購入する際には、その価格や軽さといった魅力だけでなく、こうした細かなマイナス面も把握した上で、自分のスタイルに合っているかを見極めることが大切です。
ネット上の酷評と実際のギャップ
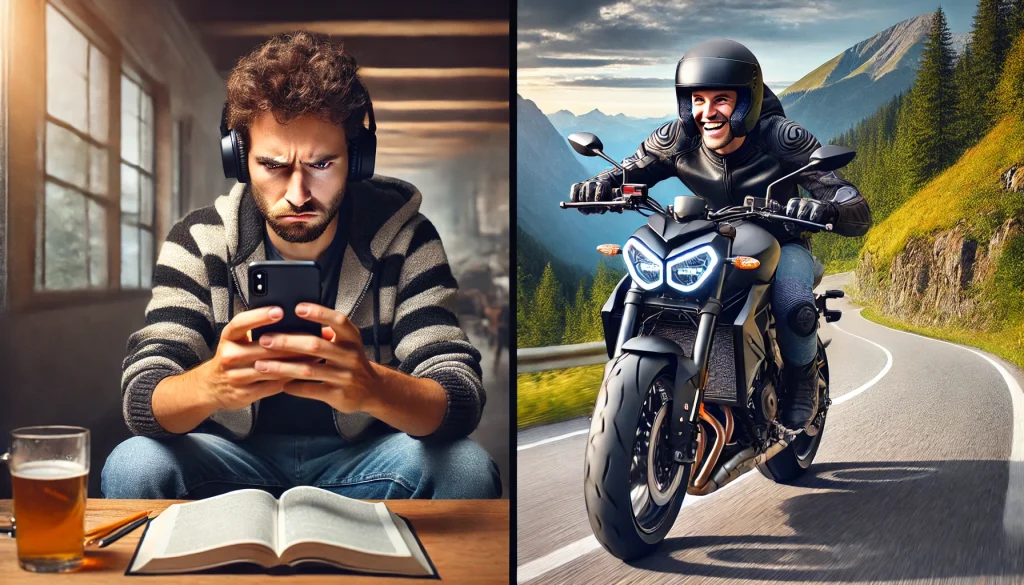
MT-07に対して「酷評」と検索される理由の一つに、ネット上の意見と実際の使用感との間にギャップがあることが挙げられます。
特に口コミやレビューサイトでは、個人的な期待値とのズレから過剰にネガティブな意見が目立つ傾向があります。
例えば、「サスペンションが貧弱」「跳ねる」「加速が急すぎて怖い」といった声が見られますが、これらの意見は乗り方やライダーの経験値によって印象が大きく異なります。
MT-07の足回りは確かにハードな走りには向きませんが、街中やツーリング用途であれば十分な性能を備えています。
また、軽量でコンパクトな車体と鋭いエンジンレスポンスは、慣れてくれば操る楽しさを感じさせてくれるポイントでもあります。
一方で、酷評の中には的確な指摘もあります。
特に初心者が最初のバイクとして選んだ場合、アクセルレスポンスの鋭さに驚いたり、リアサスの沈み込みが想像以上だったという体験談はリアルな声です。
これを「ダメなバイク」と捉えるか、「クセを理解すれば楽しめる」と捉えるかで、評価は大きく分かれます。
また、酷評が目立つ一因として、MT-07が非常に多くのライダーに選ばれているという事実も影響しています。
販売台数が多いモデルほど、意見が分かれるのは自然なことです。
その中で極端な意見が目立ってしまい、あたかも「欠点だらけのバイク」のような印象を持ってしまうことも少なくありません。
実際にMT-07に乗ってみると、ネットで見たような極端なマイナス面を感じることは少ないという声も多くあります。
むしろ、「思ったより乗りやすい」「街中での軽快さは他の大型バイクでは得られない」といった肯定的な感想が多いのも事実です。
このように、ネット上の酷評は参考になる一方で、その背景や前提条件を正しく理解しないと、誤った判断につながる恐れもあります。
実際の使用目的や自身の経験に照らし合わせながら、冷静に情報を取捨選択することが、バイク選びではとても重要です。
MT-07 酷評に関するよくある質問(FAQ)
Q1. MT-07が酷評される一番の理由は何ですか?
Q2. MT-07の持病とされる故障はありますか?
Q3. MT-07は初心者にも向いていますか?
Q4. 中古のMT-07はお得ですか?
Q5. MT-07の2025年モデルの改良点は?
Q6. 海外でのMT-07の評価は日本と違いますか?
Q7. ツアラー化カスタムのメリットとデメリットは?
MT-07 酷評に関する意見を総まとめ
-
フル加速時のレスポンスが鋭すぎて扱いづらいと感じる声がある
-
加速時に前輪が浮きやすくビギナーには難しいとの指摘がある
-
フロントサスペンションの跳ねる挙動が不安定と評価されることがある
-
高速域や峠道での足回りの安定性に不満を感じるライダーもいる
-
ブレーキの効きやタッチが曖昧とのレビューも一定数存在する
-
クラッチやアクセル操作が初心者にはピーキーに感じられる場合がある
-
長距離ツーリングではライディングポジションが疲れやすいという声もある
-
デザインや装備に豪華さがなく所有感に欠けると感じるユーザーがいる
-
レギュレーターや電装系の不調が持病として報告されている
-
スロットルレスポンスにラグを感じるという指摘も散見される
-
特定の回転域で振動が気になるとのレビューが一部にある
-
中古車はメンテナンス状態により当たり外れの差が大きい
-
海外では高評価が多いが、国内ではサス性能への酷評が目立つ
-
ツアラー化カスタムで快適性が向上する反面、軽快さが損なわれやすい
-
ネット上の酷評は乗り手の期待値とのギャップによるものも多い
ちなみに、ヤマハのバイクは「ハンドリング」や「デザイン」で選ぶのが正解と言われています。
他の排気量やジャンルも含めて検討したい方は、以下の「ヤマハ全車種・相性診断」も試してみてください。
-

-
【2026年最新】ヤマハバイク全車種図鑑|新車・名車・レンタルから「後悔しない」選び方まで徹底解説
こんにちは。双輪Log管理人のソウリンです。 「芸術的なデザイン」「ハンドリングのヤマハ」――。 ライダーを魅了してやまないヤマハ(YAMAHA)のバイク。楽器作りで培われた感性は、バイクの排気音や造 ...
続きを見る


