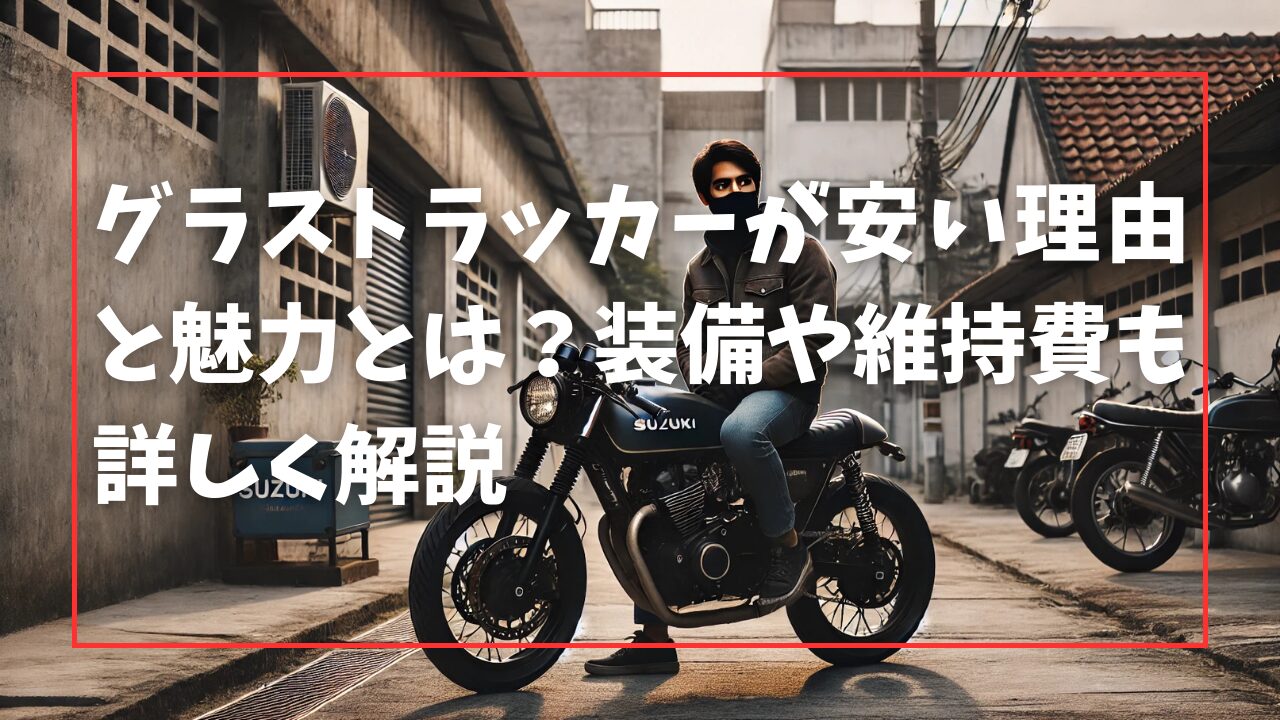グラストラッカーが安い理由が気になっているあなたは、おそらく「手頃に買えるけれど、実際どうなの?」という疑問を抱いているのではないでしょうか。
グラストラッカーは、新車販売当初からリーズナブルな価格設定がされていたバイクとして知られており、現在でも中古市場で根強い人気を誇ります。
この記事では、なぜグラストラッカーが安いのかという理由をはじめとして、カスタムの自由度やビッグボーイとの違い、寿命の目安や中古車購入時の注意点、さらには値上がりしにくい背景などを丁寧に解説します。
また、「グラストラッカーはダサい?」という評価の背景や、オフロード性能との関係、さらに当時のライバル車は?といった視点からも、このバイクの立ち位置を掘り下げていきます。
初めてバイクを買おうとしている方にも、すでに候補に挙げている方にも役立つ情報をまとめましたので、ぜひ参考にしてください。
ポイント
-
グラストラッカーの新車価格が安かった背景
-
安さと引き換えに装備がシンプルな理由
-
中古市場で値上がりしにくい要因
-
コストを抑えつつ楽しめる魅力的な特徴
【PR】いまいくら?バイク王で30秒査定してみませんか?
- いま、いくら?カンタン30秒で無料査定|出張0円・査定0円
- たった5問で完了|プロが最新相場をご案内(24時間365日受付)
- 相談実績300,000件※|まずは無料で相場チェック
スポンサーリンク
スズキ グラストラッカーが安い理由とは?

出典:SUZUKI公式サイト
当時の新車価格は?
グラストラッカーは、2000年にスズキから登場したストリートバイクで、発売当初の新車価格は384,000円で比較的リーズナブルな設定でした。
モデルや年式によって若干の差はあるものの、標準モデルでおよそ34万円〜38万円前後、ビッグボーイなどの派生モデルでも40万円台に収まることが多く、当時としてもコストパフォーマンスの高いモデルとされていました。
これは、スズキが若年層や初心者ライダーをメインターゲットにしていたことが背景にあります。
シンプルな構造と扱いやすい空冷単気筒エンジンを採用し、余計な電子制御を搭載していなかったことでコストを抑えやすかったのです。
つまり、「高機能化」に走らなかった点が価格にも反映されていました。
また、同時期に発売されていたライバルモデル、例えばヤマハのTWやホンダのFTRなどと比較しても、グラストラッカーの価格設定は抑えめでした。
そのため、バイクを始めたばかりの人や通勤・通学など日常用途を重視する層から高い支持を得ることになりました。
こうした背景から、グラストラッカーは「手軽に買えて、気軽に乗れるバイク」としてのポジションを確立し、結果的に価格の安さがブランドイメージの一部として定着したと言えます。
なぜ値上がりしにくい?
グラストラッカーが他の旧車モデルと比べて「値上がりしにくい」とされる理由は、いくつかの要因が複合的に影響しています。
市場における希少性やブランド価値、そしてバイクそのものの設計思想などが関係していると考えられます。
まず一つ目のポイントは、市場流通量の多さです。
グラストラッカーは比較的長期間にわたって販売され、多くの台数が市場に出回っていました。
したがって中古市場でも一定数の在庫があり、希少価値が付きにくい傾向にあります。
台数が潤沢に存在する以上、価格競争も起こりやすく、大きな値上がりにはつながりにくいのです。
また、コレクター向けではなく「実用バイク」としての性格が強いことも要因の一つです。
高回転型の高性能エンジンや特殊なデザインを持たないため、プレミアム価値がつきにくいという事情があります。
仮にメンテナンス状態の良い車両が見つかったとしても、それが高値で取引されるケースは限られています。
さらに、年式が進むごとに装備や仕様に大きな変化がなかったことも影響しています。
モデルチェンジによる「特別感」や「一部マニアに刺さる仕様」が少ないため、中古市場での注目度が相対的に低くなりやすいのです。
このような理由から、グラストラッカーは中古バイク市場で安定した人気を維持しつつも、旧車のような爆発的な値上がりを見せることが少ない車種だと言えるでしょう。
ライバル車はどの車種?

グラストラッカーのライバル車として代表的なのは、ヤマハのTWシリーズやホンダのFTR、さらにカワサキの250TRなどが挙げられます。
いずれも2000年代前半に流行した、ストリート向けシングルエンジンバイクという共通点を持っています。
ヤマハTW200/225は、ワイドタイヤを装備し、アウトドアテイストを前面に押し出したデザインで若者を中心に人気を集めました。
特にカスタム文化との親和性が高く、ファッション感覚で選ばれることも多かった車種です。
一方、ホンダのFTRは、フラットトラックレーサーのような軽快なスタイルと取り回しの良さが特徴です。
街中でも乗りやすく、初心者にとっても扱いやすいことから、グラストラッカーと似たようなユーザー層に受け入れられていました。
カワサキの250TRは、クラシックなスクランブラースタイルを持ち、ややレトロ寄りなデザインが好きな層に人気がありました。
こちらも軽量でシンプルな作りが魅力で、気軽にカスタムを楽しめる点で共通しています。
これらのバイクは、性能面やコンセプトにおいて極端な差があるわけではありません。
ただし、それぞれデザインや細かい乗り味に違いがあるため、好みや使用目的によって選ばれていたのが実情です。
グラストラッカーも含めたこれらの車種は、「気軽に乗れるおしゃれバイク」というカテゴリを作り上げた存在であり、今もなお多くのファンに支持されています。
寿命はどれくらい?
グラストラッカーの寿命は、整備状況や使用環境によって大きく異なりますが、一般的には走行距離でおよそ5万km〜8万km、年数でいえば15年〜20年が一つの目安とされています。
もちろん、これは「寿命=壊れて乗れなくなる」という意味ではなく、安心して乗れる状態を維持できる期間という意味です。
このモデルは、空冷の単気筒エンジンを採用しており、構造がシンプルで壊れにくいことが特徴です。
そのため、こまめなオイル交換や基本的な点検を怠らなければ、10万kmを超えても走行できる事例もあります。
バイクにあまり詳しくない人でも、基本のメンテナンスさえ押さえておけば、長く乗り続けられる車種だと言えるでしょう。
ただし、ゴム部品の劣化や電装系のトラブルなど、年式が古くなるにつれて避けられない問題も出てきます。
特にキャブレター仕様のモデルは、定期的な清掃や調整が必要で、メンテナンスを怠るとエンジン不調を招く原因にもなります。
屋外保管が長くなるとサビや腐食が進行し、足回りの寿命が縮むこともあります。
このように考えると、寿命というのは単なる数字ではなく「どれだけ大切に扱ってきたか」が大きく関係していることが分かります。
中古で購入する場合は、整備記録や保管状態も重視するとよいでしょう。
ダサいと言われる理由

グラストラッカーが「ダサい」と言われる理由には、いくつかの要素が複雑に絡んでいます。
ただし、これはあくまでも一部の意見であり、すべての人がそう感じているわけではありません。
まず、デザインに関する意見として、「シンプルすぎる」「無骨で地味」といった声があります。
グラストラッカーは、あえて装飾を排除したミニマルなスタイルが特徴ですが、それが「安っぽく見える」「古臭い印象を受ける」と捉えられることがあります。
特に現代のスポーティなデザインやLED搭載の近代的なモデルに慣れている人にとっては、クラシックで素朴な見た目が物足りなく映るのかもしれません。
また、街中での使用を想定したストリートバイクであるため、アドベンチャー系やスーパースポーツのような「迫力」や「高性能感」が感じられにくいことも、評価を分ける一因です。
とくに若年層にとっては、「カッコよさ」を前面に押し出した車種に比べると、どうしても見劣りすると感じられる傾向があります。
一方で、バイクに詳しい層からは「飾り気がないのが逆に良い」「カスタムベースとしての余白がある」といった好意的な意見も根強くあります。
つまり、「ダサい」と感じるかどうかは見る人の感性や求めるバイクのスタイルによって大きく変わるのです。
グラストラッカーは、派手さよりも「気軽に乗れること」「自分で育てていく楽しみ」を重視したバイクです。
もし、表面的なデザインだけで評価してしまうと、このバイクの本質を見落としてしまうかもしれません。
250ccクラスには他にも魅力的なバイクがたくさんあります。
「維持費の安さ」「足つきの良さ」「高速道路の快適性」など、あなたの優先順位に合わせたベストな一台を見つけるために、こちらの完全ガイドもあわせてご覧ください。
-

-
【2026年完全版】250ccバイクおすすめ人気ランキング!後悔しない選び方と維持費まで徹底解説
こんにちは、双輪Log運営者のソウリンです。 「バイクに乗りたいけど、車検でお金がかかるのは絶対に嫌だ」 「高速道路を使って遠出もしたいし、毎日の通勤でも楽に乗りたい」 そんな贅沢な悩みをすべて解決し ...
続きを見る
グラストラッカーが安い理由を徹底解説

中古市場で人気?
グラストラッカーは中古市場において一定の人気を保っているバイクの一つです。
特に若いライダーや、初めてバイクに乗る初心者からの注目度が高い傾向があります。
その背景には、価格の手頃さ、取り回しの良さ、そしてカスタムベースとしての魅力があります。
もともと新車価格が比較的安かったモデルであるため、中古でも5万円台から20万円前後まで、予算に応じた選択肢が多く揃っているのが特徴です。
さらに、車体が軽く足つき性も良好なことから、小柄なライダーや女性ユーザーにとっても扱いやすいバイクといえるでしょう。
こうした条件が重なることで、需要の安定につながっていると考えられます。
また、グラストラッカーはエンジン構造がシンプルで、メンテナンスのしやすさでも評価されています。
キャブレター仕様で整備がしやすいため、バイクの仕組みを学びたいという人にも向いており、レストアやカスタムを楽しむ層からも支持されています。
ただし、人気があるとはいえ、絶対的な玉数は年々減ってきており、状態の良い車体は年式の割に高値で取引されるケースも増えています。
購入を検討する際は、整備記録やエンジンの始動状態などをよく確認し、信頼できるショップから購入することが重要です。
このように、中古市場においてグラストラッカーは“安くて遊べるバイク”として、今でも多くのライダーにとって魅力的な選択肢となっています。
カスタムの自由度は?
グラストラッカーは、カスタムの自由度が高いバイクとして広く知られています。
その理由は、車体構造がシンプルで余計な装飾が少なく、いわば“白紙のキャンバス”のような存在だからです。
ノーマルの状態では、ストリート寄りの無骨で控えめなスタイルですが、パーツの交換や追加によって、カフェレーサー風やスクランブラー仕様、あるいはヴィンテージテイストに仕上げることも可能です。
たとえば、シートをスリムなソロタイプに替えたり、ハンドルをセパレートに変えるだけでも、印象は大きく変化します。
マフラーやヘッドライト、ウインカー類も社外製品が多く流通しており、パーツ探しの楽しみもあるでしょう。
また、フレームの加工を必要としないボルトオンパーツが充実しているため、専門知識がない人でも手軽にカスタムに挑戦しやすいというメリットがあります。
自分のセンスに合ったスタイルを少しずつ作っていく楽しみは、バイクライフそのものを豊かにしてくれるはずです。
一方で、あまりに自由度が高いがゆえに、方向性を見失いやすいという側面もあります。
カスタムの方向性に統一感がないと、ちぐはぐな印象になることもあるため、あらかじめ完成イメージを明確にしてから手を加えることが大切です。
このように、グラストラッカーは“自分だけの一台”を作る喜びを感じさせてくれるバイクであり、カスタムに興味があるライダーにとっては非常に魅力的な選択肢です。
ビッグボーイとの違いは?

グラストラッカーには、「ビッグボーイ」というバリエーションモデルが存在します。
名前は似ていますが、両者にはいくつかの明確な違いがあるため、購入や比較の際にはポイントを押さえておくとよいでしょう。
最大の違いは「足回りとサイズ感」です。
ビッグボーイはフロントタイヤが19インチ、リアが18インチで、標準モデルより一回り大きめに設計されています。
これにより、見た目に存在感が増し、走行時の安定感も若干向上しています。
サスペンションのストロークも長めに設定されており、段差やちょっとした悪路でも安心して走ることができます。
また、車高が高くなっているため、足つき性はグラストラッカーより劣る場合があります。
特に小柄なライダーにとっては、シート高の違いが乗り心地に大きく影響するため、実車にまたがって確認するのがおすすめです。
一方で、エンジンや基本的な車体構造は共通しており、メンテナンス性や燃費性能に大きな差はありません。
カスタムパーツについても多くが共通しており、ビッグボーイをベースにしたカスタム事例も数多く見られます。
こう考えると、グラストラッカーはよりコンパクトで扱いやすく、ビッグボーイはよりダイナミックな印象と走破性を求める人向けのモデルといえます。
どちらを選ぶかは、乗るシーンや体格、そして好みのスタイルによって決めるのが良いでしょう。
グラストラッカービッグボーイ スペック表
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| モデル名 | グラストラッカービッグボーイ |
| 型式 | JBK-NJ4DA |
| 発売年/月 | 2014年6月 |
| 中古車価格帯 | 19万円〜79.8万円 |
| 中古車台数 | 69台 |
| ユーザーレビュー | 4.2点(評価人数:67人) |
| 全長 | 2,200mm |
| 全幅 | 910mm |
| 全高 | 1,145mm |
| ホイールベース | 1,405mm |
| 車両重量 | 139kg |
| シート高 | 790mm |
| エンジン | 空冷4ストローク単気筒 SOHC2バルブ |
| 排気量 | 249cc |
| 最高出力 | 19PS/7,500rpm |
| 最大トルク | 21Nm/5,500rpm |
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション |
| 燃費(60km/h) | 48.0km/L |
| タンク容量 | 8.4L |
| 満タン航続距離 | 約403km |
| 変速機 | リターン式・5段変速 |
| 始動方式 | セルフスターター |
| フレーム形式 | ダイヤモンド型 |
| 前タイヤ | 100/90-19 |
| 後タイヤ | 130/80-18 |
| ブレーキ(前) | 油圧式ディスク |
| ブレーキ(後) | 機械式リーディングトレーリング |
オフロード性能はどう?
グラストラッカーは一見するとストリートバイクに見えますが、その成り立ちや構造にはオフロード由来の要素が含まれています。
そもそもこの車種は、スズキのオフロードバイク「DR250」がベースとなっており、そのフレームやエンジン特性は、舗装路以外の走行もある程度想定された設計となっています。
実際、軽量な車体やアップタイプのマフラー、比較的ストロークの長いサスペンションなど、オフロードバイクとしての名残がいくつも見られます。
また、シート幅が細く、足つきが良いことから、立ち乗りや姿勢変化がしやすく、未舗装路でのちょっとした悪路走行にも対応可能です。
ただし、純粋なオフロードモデルと比較すると、本格的なダート走行にはやや不向きです。
タイヤはオンロード向けが標準装備で、サスペンションの強度やクリアランスも専門モデルほどではありません。
このため、林道ツーリングやフラットダート程度であれば十分に楽しめますが、泥や岩場を含むようなハードなオフロードでは性能の限界が見えてくるでしょう。
それでも、街乗り中心で時折オフロードに足を踏み入れたいというライダーにとっては、グラストラッカーはちょうどいいバランスの車種と言えます。
見た目のスタイリッシュさと、オフにも対応できる構造の両立が、このバイクの魅力の一つです。
安さと引き換えの装備面の特徴

グラストラッカーが安価に提供されている理由の一つには、装備面での“シンプルさ”があります。
高級装備を排した設計となっており、バイクとしての基本性能には支障がないものの、近年のモデルと比較すると見劣りする部分も見られます。
まず、メーター類は最低限の情報表示にとどまり、タコメーターは装備されていません。
燃料計もないため、燃料管理は距離計を頼りに行う必要があります。
こういった点は、初めて乗る人にとって少し不便に感じられるかもしれません。
さらに、セルスターターは装備されていますが、キックスタートが併用されているモデルも多く、現代の利便性に慣れていると古さを感じる部分です。
また、ブレーキは前後ディスクとドラムの組み合わせで、制動力の面では現行のABS付きモデルに比べてやや控えめです。
その一方で、この装備の簡素さが整備のしやすさや故障リスクの少なさにつながっており、メンテナンス費用の軽減や初心者にも扱いやすいというメリットがあります。
電子制御に頼らない構造は、バイク本来の操作感を楽しみたいという人にとって、むしろプラスに働く場面もあるでしょう。
このように、グラストラッカーの価格の安さは、装備を必要最小限に抑えることで実現されています。
利便性と快適性をどこまで求めるかによって、この装備構成をどう受け取るかが変わってくるはずです。
維持費とコスパのバランスを考える
グラストラッカーは、維持費の面でも比較的優れたコストパフォーマンスを発揮するバイクです。
軽量でシンプルな構造が、ランニングコストの抑制に一役買っており、日常的にバイクを使いたい人にとって魅力的な選択肢となっています。
まず、燃費性能が優秀です。
街乗り中心であればリッター30〜35km程度走ることも珍しくなく、燃料代が高騰している昨今においては経済的なメリットを感じやすいでしょう。
排気量も250ccクラスであるため、自動車税や保険料も比較的安く済みます。
整備に関しても、キャブレター式エンジンであることから、自分でメンテナンスしやすく、部品代も高額ではありません。
消耗品の交換も一般的な価格帯で済み、修理費用が膨らみにくいという利点があります。
バイクショップによっては、パーツの在庫が豊富にあるため、修理の際もスムーズに対応してもらえることが多いです。
ただし、古いモデルであるため、状態によっては突発的な修理が発生する可能性もあります。
特に中古車を購入する際には、メンテナンス履歴の確認や、事前の点検を怠らないことが重要です。
このように見ていくと、グラストラッカーは“安く買って、安く維持できる”という特徴を備えており、日常の足から趣味としてのバイクライフまで、幅広く対応できるバイクです。
初期投資と日々の維持費のバランスを考えると、非常にコスパに優れた一台だと言えるでしょう。
スペック表
| グラストラッカー スペック・特徴まとめ | |
|---|---|
| モデル概要 | 1970年代の草レーサーをイメージしたファッショナブルなストリートバイク |
| 特徴 | シンプルでスリムなデザイン、ファッショナブルな小型部品装着 |
| 全長 | 1,995mm |
| 全幅 | 900mm |
| 全高 | 1,130mm |
| 軸間距離 | 1,325mm |
| 車両重量(乾燥) | 124kg |
| エンジン種類 | 空冷4サイクル単気筒 SOHC4バルブ |
| 総排気量 | 249cc |
| ボア×ストローク | 72mm × 61.2mm |
| 最高出力 | 15kW(20ps)/ 7,500rpm |
| 最大トルク | 21Nm(2.1kgm)/ 6,000rpm |
| 変速機形式 | 常時噛合式5段リターン |
| タイヤサイズ(前) | 3.00-18 47S |
| タイヤサイズ(後) | 120/80-17 61S |
| 発売当時の価格 | 384,000円 |
| 派生モデル | ビッグボーイ(フロントフォークとスイングアーム延長、タイヤ径拡大) |
グラストラッカーが安い理由に関するよくある質問(FAQ)
Q1. グラストラッカーが安い理由は何ですか?
Q2. 新車価格はいくらでしたか?中古の相場は?
Q3. 値上がりしにくいと言われる理由は?
Q4. 維持費や燃費はどのくらいですか?
Q5. 中古で買うときの注意点は?
グラストラッカーが安い理由を総まとめで解説
-
新車当時の価格設定が34〜38万円前後と低価格だった
-
若年層や初心者ライダーをターゲットにしていた
-
装備をシンプルにすることで製造コストを抑えていた
-
高度な電子制御を採用せずコストダウンに成功していた
-
空冷単気筒エンジンにより整備性とコストの両立を図っていた
-
競合モデルと比べても価格が抑えられていた
-
市場流通台数が多く希少価値が付きにくい
-
プレミアム感やコレクター性が低く価格が上がりにくい
-
装備の簡素化で修理・部品交換コストが低い
-
メーターや電装が最低限で維持費が抑えられる
-
ABSなどの高価な安全装備が搭載されていない
-
キャブレター式で構造が簡単かつ自己整備がしやすい
-
モデルチェンジによる装備変化が少なく値崩れしにくい
-
実用バイクとしての需要が安定している
-
カスタムベースとして人気があり中古市場でも手頃な価格帯が維持されている
「スズキのバイクはコスパが良いって聞くけど、他にはどんな車種があるの?」
「“変態”と呼ばれる独自技術や、鈴菌(スズキファン)の世界をちょっと覗いてみたい」
そんな方のために、現在購入可能なスズキの全ラインナップ(現行・名車)の特徴や選び方を、ひとつの図鑑にまとめました。
質実剛健にして独創的。一度ハマると抜け出せないスズキワールドの全貌は、こちらからチェックできます。
-

-
【2026年最新】スズキバイク全車種図鑑|コスパ最強?変態?スズキ愛あふれる選び方ガイド
こんにちは。双輪Log管理人のソウリンです。 「コスパ最強」「独自のメカニズム」「変態(褒め言葉)」――。 他のメーカーにはない独特の魅力で、一度ハマると抜け出せない熱狂的なファン(通称:鈴菌)を生み ...
続きを見る