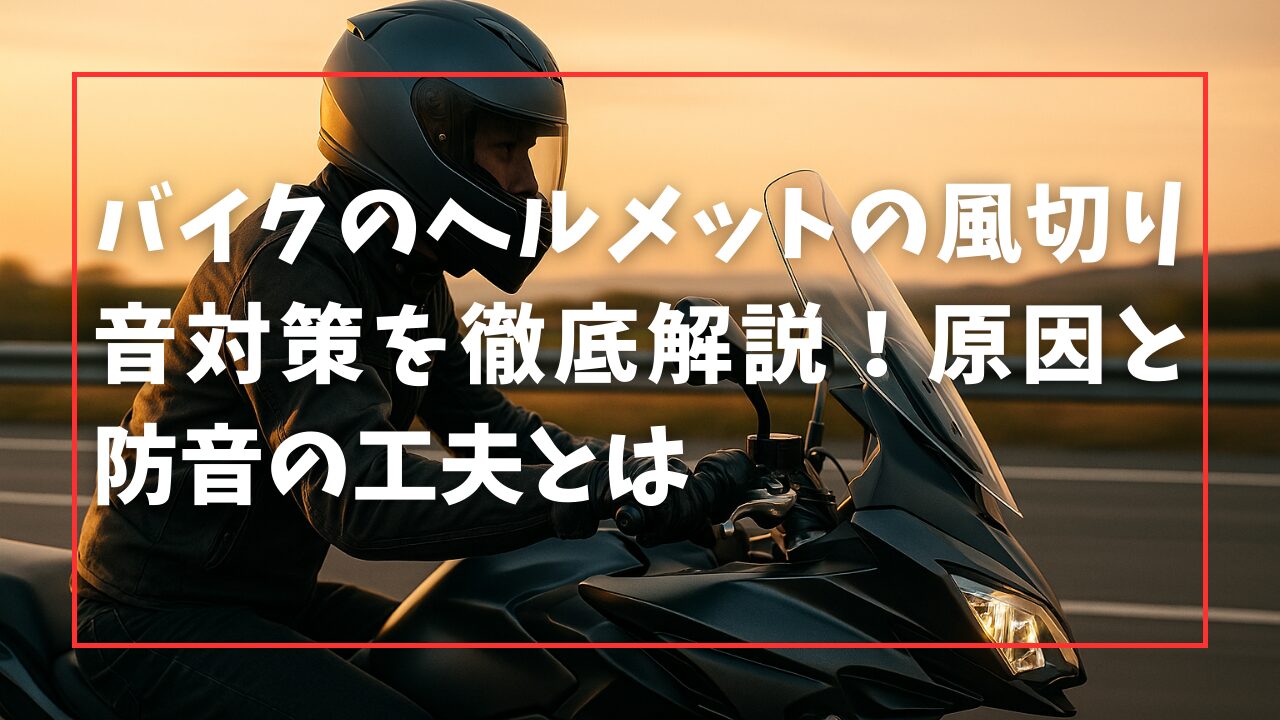バイクを日常の移動手段や趣味として楽しむライダーにとって、ヘルメット選びは快適性と安全性の両面で非常に重要なポイントです。
中でも、多くのライダーが悩まされているのが「風切り音」。
この騒音の原因は、ヘルメットの形状やフィット感、シールドの密閉性などさまざまで、対策を怠ると疲労や集中力の低下にもつながります。
本記事では、フルフェイス・システムヘルメット・ジェットヘルメットといった各種タイプの特徴や、それぞれの風切り音対策の具体例を紹介していきます。
特に注目度の高いカブトヘルメットやWINSの静粛性に関する評価、装備選びのコツもあわせて解説します。
また、静かで快適なヘルメット静粛性ランキングも取り上げ、ヘルメット選びの参考にしていただける内容になっています。
バイクに乗るたびに気になる風切り音の原因を正しく理解し、自分に合った対策を講じることが、快適なライディング環境を手に入れる第一歩となるでしょう。
ポイント
-
風切り音が発生する主な原因とその仕組み
-
ヘルメットの種類ごとの風切り音対策方法
-
装備や外部アイテムによる騒音の軽減手段
-
静粛性に優れたおすすめヘルメットの選び方
【PR】いまいくら?バイク王で30秒査定してみませんか?
- いま、いくら?カンタン30秒で無料査定|出張0円・査定0円
- たった5問で完了|プロが最新相場をご案内(24時間365日受付)
- 相談実績300,000件※|まずは無料で相場チェック
スポンサーリンク
バイクのヘルメットの風切り音対策の基本

風切り音の原因を知ろう
ヘルメットにおける風切り音の発生原因を理解することは、快適なライディング環境を手に入れるための第一歩です。
風切り音とは、走行中にヘルメット周囲の空気が乱れたり、ヘルメット表面を高速で通過したりすることで発生する音のことを指します。
特に高速道路などでは音量が大きくなり、長時間の走行では疲労や集中力の低下を招く原因になります。
風切り音の主な要因は大きく分けて3つあります。
1つ目は「ヘルメットの形状」。流線型ではないデザインや、突起の多い形状は空気の流れを乱し、騒音の原因となります。
2つ目は「通気口(ベンチレーション)やシールドの隙間」です。
わずかな隙間から風が入り込むと、そこに乱流が発生し、耳元に直接響くようなノイズが発生します。
そして3つ目は「ライダーの姿勢や体格」。乗車時の前傾姿勢や肩幅などが空気の流れを変え、結果的にヘルメット周辺の気流が不安定になることがあります。
また、ヘルメットの種類や素材によっても風切り音の発生度合いは異なります。
軽量素材で作られたモデルは振動しやすく、内部の共鳴によって風切り音が増幅されるケースもあります。
逆に、適切な遮音構造を持つヘルメットであれば、外部のノイズが効果的にカットされるため、静かな環境を実現できます。
つまり、風切り音はヘルメット単体の問題ではなく、設計・装着状態・ライディング環境など、複数の要因が絡み合って生じるものです。
そのため、音の発生源を正しく把握したうえで、状況に応じた対策を講じることが重要になります。
フルフェイスの対策のコツ
フルフェイスヘルメットでの風切り音を抑えるには、構造上の特性を理解したうえで、いくつかの工夫を取り入れることが効果的です。
フルフェイス型はもともと密閉性が高いため、他のヘルメットに比べて風切り音が少ない傾向にあります。
しかし、完全ではなく、特にシールド周辺やベンチレーション部分から音が侵入しやすいため注意が必要です。
まず、対策の基本として「フィット感の高いモデルを選ぶ」ことが挙げられます。
頭のサイズに合わないヘルメットを使用すると、内部に隙間が生じ、空気が入り込みやすくなります。
また、顎下に隙間があると、風が巻き込んでヘルメット内部で共鳴し、ノイズの原因となることもあります。
チンカーテン(あご下の風よけ)を活用することで、この隙間を埋め、風の侵入を大幅に減らすことができます。
次に、「シールドの密閉性」をチェックすることも忘れてはいけません。
経年劣化によってシールドのゴムパッキンが摩耗していたり、取り付けが甘くなっていたりすると、そこから風が入り込み、音が発生します。
定期的にシールドの状態を確認し、必要に応じて交換することが有効です。
また、ヘルメットのベンチレーションを使う際は、開けた状態での風切り音が気になる場合、走行状況に応じて一部を閉じることも有効です。
さらに、ライディング時の頭の角度を少し下げるだけでも、風の流れをスムーズにし、騒音を減らせる場合があります。
これらの対策を組み合わせることで、フルフェイスヘルメットの静粛性を高め、より快適なツーリングを楽しむことができるでしょう。
システムヘルメットの風切り音を減らす工夫

システムヘルメットはその構造上、フルフェイス型に比べて風切り音が発生しやすいと言われています。
特にチンバー(あご部分)の開閉構造による可動部が多いため、隙間から風が侵入しやすくなります。
ただし、いくつかの設定や工夫を行うことで、風切り音を効果的に抑えることは可能です。
まず重要なのは、「正しく締める」ことです。
あご部分のロックが甘いと、走行中にわずかな振動でもズレが生じ、隙間から風が入ってしまいます。
チンバーのロック機構が確実に固定されているかを毎回確認する習慣をつけましょう。
次に、「シールドとチンカバーの接合部」を見直すことも有効です。
特に開閉を繰り返すうちに密閉性が低下しているケースがあります。
そのため、メーカーが推奨する定期的なメンテナンスや、ゴムパーツの交換を怠らないようにしましょう。
さらに、風切り音を減らすには「インナーパッドの調整」も見逃せません。
多くのシステムヘルメットでは、内装のパッドを追加・交換することで、頭部や耳周辺の密着度を高めることができます。密着度が高くなることで、外部からの騒音が侵入しにくくなります。
また、走行中の姿勢も一つのポイントです。
特にシステムヘルメットは上方向の空気抵抗を受けやすいため、ヘルメットの前傾角度を意識して調整することで、風の流れを安定させ、結果として風切り音の発生を抑えることができます。
このように、システムヘルメット特有の構造を理解し、日々の使用やメンテナンスに注意を払うことで、風切り音は確実に軽減できます。
静粛性を重視したツーリングを目指すのであれば、こうした細かな設定の積み重ねが大きな効果を生み出すでしょう。
ジェットヘルメットの対策と通勤対応
ジェットヘルメットは視界の広さや装着のしやすさから、通勤用として非常に人気があります。
ただし、構造的に開放部分が多く、風切り音が大きくなりやすい点には注意が必要です。
特に毎日の通勤で長時間バイクに乗る場合、この風切り音がストレスになるケースも珍しくありません。
ジェットタイプはあご部分が露出しているため、走行中に正面から風を直接受けやすい構造です。
この風がヘルメット内部に入り込み、耳元で共鳴するように響くことで、耳鳴りや疲労の原因となることがあります。
また、冬場など風が冷たい季節では、風切り音と同時に寒さも感じやすく、防寒性の面でも課題があります。
しかし、ジェットヘルメットであっても、いくつかの工夫によって通勤時の快適性は大きく向上します。
例えば、専用のスモークシールドやロングバイザーを装着することで、風の巻き込みを軽減できます。
さらに、シールドの隙間に貼る「風切り音防止テープ」などの市販アイテムを使えば、空気の侵入をかなり抑えることが可能です。
もうひとつの対策として、「ネックウォーマー」や「ウィンドガード付きのインナー」を組み合わせて着用する方法があります。
これにより首回りから侵入する風をカットし、結果として風切り音の低減にもつながります。
実際、多くの通勤ライダーがこのような工夫を取り入れて、ジェットヘルメットでも静かで快適な通勤を実現しています。
日々の通勤にバイクを使用する場合、こうした細かな対策が積み重なることで、疲労の蓄積を防ぎ、集中力を保つことができます。
特にジェットタイプを選ぶ場合は、防風対策と風切り音対策を同時に行うことが、快適なライディングへの鍵となります。
風切り音を静かにする装備選び

ヘルメットの風切り音を静かにするには、ヘルメット本体の選び方だけでなく、周辺装備にも注目する必要があります。
装備選びを見直すことで、思っている以上に走行中の音を抑えることができ、快適性や集中力の向上にもつながります。
まず、静粛性を意識したヘルメットを選ぶ際は、遮音構造に優れたモデルを選ぶのが基本です。
内装のパッドが厚く、耳周辺にぴったりとフィットする構造であれば、風の侵入だけでなく音の伝導も抑えることができます。
また、空力性能が高く、風の流れを整えるシェル形状を採用したヘルメットは、自然と風切り音も少なくなる傾向があります。
そして、意外と見落としがちな装備が「耳栓」や「ノイズリダクションインナー」の使用です。
ツーリング用に開発された高性能耳栓の中には、必要な周囲の音は残しつつ、不快な風切り音だけをカットしてくれる製品もあります。
これを使うことで、音疲れを防ぎ、長時間のライディングでも快適な環境を維持できます。
さらに、装備全体の中でも重要なのが「インカムのスピーカー配置」です。
スピーカーの位置が耳とずれていると、ボリュームを上げざるを得なくなり、風切り音と相まって騒音の原因となります。
スピーカーと耳がしっかり重なるように調整することで、結果的に音量を下げても聞こえやすくなり、風切り音の存在感も抑えることができます。
最後に、バイク自体の装備も一緒に考えるとより効果的です。
例えば、高さのあるウィンドスクリーンを取り付けると、ヘルメットに直接風が当たらなくなり、そもそもの風切り音を大幅に抑えることが可能です。
このように、ヘルメット本体に加えて、耳元の装備やバイク側の工夫も含めた総合的な対策が、風切り音の少ない快適なライディングを実現するカギとなります。
バイクのヘルメットの風切り音対策の実践法

静粛性の高いヘルメットランキング
ヘルメットを選ぶ際、「静粛性」を重視するライダーは少なくありません。
特に長距離ツーリングや高速道路を頻繁に利用する方にとって、ヘルメット内部の騒音レベルは快適さや疲労度に直結します。
ここでは、静粛性に定評のあるフルフェイス型を中心に、2025年時点で注目されているヘルメットのランキングを紹介します。
まず、最も静粛性が高いと評価されているのが SHOEI Z-8 です。
空力性能が極めて高く、風を受け流す形状により風切り音を最小限に抑えています。
内装も耳まわりをしっかり覆う設計で、ノイズの侵入を徹底的にガードしています。
加えて、密閉性の高いシールド構造も静音性を高めるポイントとなっています。
次点で評価されているのが Arai Quantic です。
Arai特有の丸みを帯びたデザインにより、空気抵抗を分散しやすく、風による不快な音の発生を防ぎます。
また、シェル全体にわたる精密な成形技術により、内部共鳴も抑えられており、実走時の静かさに驚くユーザーも少なくありません。
続いて Kabuto KAMUI-3 も高評価を得ています。
日本人の頭型にフィットしやすい設計が好評で、顔まわりに無駄な隙間ができにくいため、風切り音の侵入を大幅に防ぐことができます。
さらに、内装の遮音性にも力が入れられており、国内ユーザーの通勤や街乗りにも適した静音モデルといえるでしょう。
このように、静粛性の高いヘルメットは、単に「静か」であるだけでなく、構造や素材、設計思想そのものが快適性を意識して作られています。
特に高速巡航や長時間の走行が多い方は、価格だけでなく「静粛性の実力」で選ぶことが、満足度の高い購入につながります。
WINSヘルメットの風切り音対策の評価は?
WINS(ウインズ)ヘルメットは、コストパフォーマンスの良さや多機能性が注目される国産ブランドです。
中でも風切り音対策に力を入れているモデルが複数あり、ユーザーからの評価も年々高まっています。
とくに「X-ROAD」シリーズなどは、実際の使用感に基づいた改良が加えられており、エントリーユーザーからツーリング愛好者まで幅広い支持を得ています。
WINSの風切り音対策は、主に「空気の流れを整えるデザイン」と「密閉性の高いシールド構造」の2点に集約されます。
ヘルメットの上部や後頭部に設けられたエアロフィンの効果により、風の乱れを防ぎ、ヘルメット全体が揺れるような振動音を抑制しています。
また、シールド部分には「ダブルシール構造」を採用しているモデルもあり、外気の侵入とともに風の音も大きく軽減される設計です。
さらに、近年のモデルでは標準でチークパッドの厚みを調整できるようになっており、自分の顔にフィットさせることで風の侵入ポイントを細かく調整できる点もメリットです。
こうした調整機能は、風切り音の対策だけでなく快適性にも直結します。
一方で、上位モデルと比較すると「極端に静か」というわけではなく、やや風切り音が残る場面もあります。
特に高速域での連続走行では、SHOEIやAraiといったハイエンドブランドと比べてやや音が耳に残るという意見も見られます。
ただし、その差は大きな問題ではなく、価格を考えれば十分に納得できるレベルと言えるでしょう。
総じて、WINSの風切り音対策は「バランス型」とも言える内容で、価格・性能・静粛性のトータルで見れば非常に優秀な選択肢です。
はじめてのヘルメット選びや買い替え時に、風切り音対策とコストを両立させたい方におすすめできるブランドです。
OGKカブトヘルメットの風切り音はどう?

OGKカブトのヘルメットは、国内ライダーに長年愛されてきた実績のあるブランドであり、風切り音への対策についても継続的に改善が行われています。
特に注目すべきは、日本人の頭型に特化したフィット感と、風洞実験を活かしたエアロダイナミクス設計です。
これにより、風切り音の抑制とライディング時の安定性を両立しています。
カブトの代表的なモデル「AEROBLADE-6」や「KAMUI-3」では、空気の流れを計算したシェル形状とエアインテークの配置が特徴的です。
これにより、風を効率よく後方へ流すことができ、結果的に風がヘルメット表面で乱れることによって発生する風切り音を大幅に軽減しています。
さらに、チークパッドの密閉性が高く、耳周辺への風の巻き込みを効果的に防ぐ構造となっています。
また、シールドの密着度にも工夫が施されており、走行中でもシールドが浮きにくい構造となっている点も、静粛性に大きく影響しています。
シールドとヘルメットの隙間が少ないことで、風が入り込みにくくなり、ヘルメット内部で発生する風音も自然と抑えられるのです。
ただし、どのモデルも万能ではなく、通気性を優先した場合には風切り音がやや目立つこともあります。
特に夏場の使用ではベンチレーションを全開にすることが多くなり、その分風の侵入量が増えるため、音が気になることもあるでしょう。
この点は、快適性と静粛性のトレードオフとして理解しておくとよいかもしれません。
このように、カブトのヘルメットは「実用性の中に静粛性を取り入れる」姿勢が強く、日常使用からツーリングまで幅広いシーンに対応できます。
風切り音に配慮しつつ、日本の気候や体型に合った製品を求める方には、非常にバランスの良い選択肢となるでしょう。
耳栓・ネックカバーなど外部アイテム
風切り音対策としてヘルメット本体の性能に注目が集まりがちですが、実は「外部アイテム」の活用によって大きな効果が期待できます。
特に耳栓やネックカバーといった補助アイテムは、手軽に導入できるうえ、コストパフォーマンスにも優れているため、多くのライダーにおすすめです。
まず耳栓についてですが、これは直接耳に装着することで風切り音やエンジン音などを物理的に遮断するアイテムです。
ライダー向けの耳栓は、音を完全に遮るのではなく「必要な音だけを通す」構造になっているものが多く、安全性を損なわずに使用できます。
例えば、エンジン音や周囲の車の存在を感じながら、風のノイズだけを軽減できるタイプが人気です。
素材はシリコンやウレタンなどがあり、長時間装着しても痛くなりにくいものを選ぶことがポイントです。
次にネックカバーは、首元からの風の侵入を防ぐことで、ヘルメット内部に流れ込む気流をコントロールする役割を果たします。
特にフルフェイスでも顎下に隙間ができやすいモデルでは、ここから風が入り込み、耳元でノイズを生むケースが少なくありません。
ネックカバーを装着することで、この隙間を物理的に塞ぎ、風の巻き込みによる風切り音を抑えることができます。
その他、シールド下部に取り付ける「チンカーテン」や「ウインドジャマー」といった補助パーツも効果的です。
これらはヘルメットに後付け可能なパーツで、空気の侵入経路を絞ることで騒音対策になります。
こうしたアイテムは、ヘルメットの性能に頼らずとも、工夫次第で風切り音を大きく減らすことができる貴重な手段です。
特に買い替えをまだ考えていない方にとっては、今すぐ試す価値がある対策といえるでしょう。
点検と寿命から見た買い替え判断

ヘルメットはバイク用品の中でも命を守る最も重要なアイテムですが、その「買い替え時期」を見極めるのは意外と難しいものです。
見た目に異常がないとつい使い続けてしまいがちですが、風切り音の増加や装着感の変化には、ヘルメットの劣化が影響している可能性があります。
まず、ヘルメットには使用年数に応じた「寿命」があります。
多くのメーカーは、安全性や素材の劣化を踏まえて、おおよそ3〜5年を推奨寿命としています。
これは外装の衝撃吸収能力だけでなく、内装のクッションやパッドのへたり、接着剤の劣化、通気パーツの損傷なども関係しています。
こうした劣化が進行すると、内部の密閉性が下がり、結果として風切り音が大きくなってしまうのです。
ここで注目すべきは「定期的な点検」の重要性です。
例えば、シールドの締まり具合が緩くなっていたり、内装パッドが潰れて耳周りに隙間ができていたりすると、音が侵入しやすくなります。
また、ベンチレーション機構が破損して空気の流れを制御できなくなるケースもあります。
これらの症状が見られたら、買い替えを検討する合図と考えて差し支えありません。
さらに、転倒や落下によって目に見えない内部構造にダメージが加わっている場合もあります。
このような場合、外見では問題なさそうでも、衝撃吸収力が低下している可能性があるため、安全性は保証できません。
加えて、経年による素材の硬化やひび割れなども、風切り音や快適性に影響する要素となります。
このように、風切り音が気になるようになってきた場合、それは単なる騒音の問題にとどまらず、ヘルメットそのものの劣化サインかもしれません。
快適性と安全性の両方を確保するためにも、見た目だけでなく機能面から定期的にチェックし、適切なタイミングで買い替えを行うことが重要です。
バイクのヘルメットの風切り音対策に関するよくある質問(FAQ)
Q1. ヘルメットの風切り音が発生する主な原因は?
Q2. 一番静かなのはフルフェイス?システムやジェットとの違いは?
Q3. システムヘルメットの風切り音を減らすコツは?
Q4. ジェットヘルメットでも静かにできますか?
Q5. 走行姿勢やスクリーンは風切り音に影響しますか?
Q6. シールドやベンチレーション設定の最適解は?
Q7. 耳栓は安全面で大丈夫?法的な問題は?
Q8. インカムを使うと逆にうるさくなります。対策は?
Q9. チンカーテンやネックカバーの効果はどのくらい?
Q10. 風切り音が増えたら買い替え時ですか?寿命の目安は?
Q11. フィットが甘いとどれくらい影響しますか?選び方は?
Q12. 今すぐできる簡単な風切り音対策は?
バイクのヘルメットの風切り音対策のポイントを総まとめ
-
ヘルメットの形状やデザインが風切り音の大きな要因となる
-
ベンチレーションやシールドの隙間から風が入り乱流が発生する
-
ライダーの姿勢や体格も気流を乱し騒音の原因となる
-
軽量素材のヘルメットは共鳴しやすく風切り音が増す
-
遮音構造のあるモデルはノイズを効果的に抑制できる
-
フルフェイスヘルメットは密閉性が高く風切り音に強い
-
チンカーテンの装着で顎下からの風の侵入を防げる
-
シールドの劣化や密閉不良は風音の増加に直結する
-
システムヘルメットは可動部が多く騒音リスクが高い
-
ロック機構やパッドの調整で密閉性を高められる
-
ジェットヘルメットは構造上風切り音が大きくなりやすい
-
ロングバイザーや風切り音防止テープで騒音を軽減可能
-
高性能耳栓やネックカバーの活用でノイズ対策を強化できる
-
インカムのスピーカー位置も音量調整と騒音軽減に影響する
-
ヘルメットは3〜5年が寿命の目安で劣化が騒音を招く要因になる
この記事では特定のお悩み解決法を紹介していますが、根本的な解決には「自分に合ったヘルメット選び」が重要です。
以下の記事では、機能性や快適さを重視したヘルメットの選び方を徹底解説しています。
-

-
【完全版】失敗しないバイクヘルメットの選び方|おすすめメーカーから洗い方・捨て方まで徹底網羅
バイクに乗る上で、最も重要かつ、ライダーの個性を一番主張できるアイテム。それが「ヘルメット」です。 「とりあえず何でもいいや」で選んでいませんか? 実は、ヘルメット選びを間違えると、ツーリング中に頭が ...
続きを見る